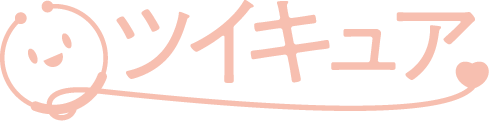くるみアレルギーの経口負荷試験について
10歳未満男性
3歳児です。くるみアレルギーと診断され、医師からの指示は「食べなくても困るものではないから食べないように」とのことでした。
ですが食品パッケージを見ると原材料ではなくても「製造ラインが同じ」等というものもあり、また原材料には記載がないが原材料のそのまた材料に使われていることもあるという話も聞きました。
どの程度除去すべきか(上記のようなケースは除去しなくてよいのか)判断に迷っていますが、先生はどのようにお考えになるでしょうか。
食べられる量を知るためには経口負荷試験を受ける必要があると思うのですが、くるみはアレルギー反応が激しいので経口負荷試験をしないとも耳にしました。くるみに対する経口負荷試験についてのお考えもお聞かせいただければ幸いです。
なおアレルギーと診断された経緯は、くるみ(1mmほどのかけらを3粒程)の摂取後、発疹、腹痛、咳が出て受診、採血でIgEを調べた上での診断です。
回答済み